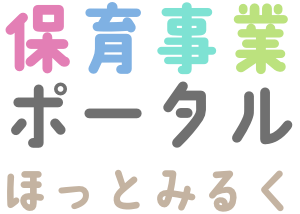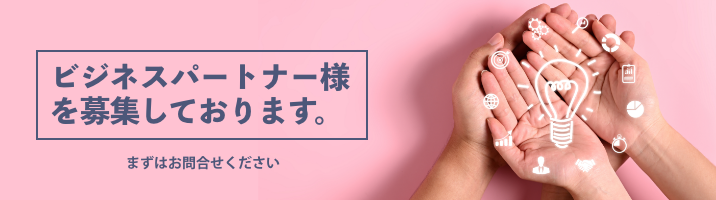| 開催日 | 2023年07月17日 〜2023年07月17日 |
|---|---|
| 開催時間 | 7:30 pm 〜9:30 pm |
| 開催場所 |
※URLは イベント詳細リンクをご確認ください。 |
| 料金 | 有料 |
| 開催団体名 | シェルハブ・メソッド しおがま |
| 開催団体サイト | |
| イベント詳細 |
動きを見る力を養うための ●なかなかお座りしない 赤ちゃんやご家族に接する方はもちろん * * * ①こんなことに困っていませんか?
「動きが気になる子に、何かしてあげたい」 そんな方におすすめのレッスンをお届けします。
「子どもを変えよう」と考えると、大変だし、しんどい! 小さな動き、小さな変化、小さな成長が見えるようになります。
寝返りやハイハイをしてみる・・・のではなく、 赤ちゃんの動きなのですが 「難しい」と感じたら、新しい動きや
動きを見るチカラが育つと、こんな変化が。 「まだ○○しないんです」 という相談に、お子さんの小さな変化をお伝えできるようになったのがよかった!(保育士・子育て支援センター勤務) また、自分の体や動き、気持ちの変化があった! 「日常でも体幹や背骨、骨盤や股関節の動きを意識するようになった」
◎子どもの動きが気になる! ・・・逆に、こんな方には向かないかもしれません。 ✖「正しい方法」「正しい動き」を知りたい
「経験したことがない動きは、できない」 これはシェルハブ・メソッドの基本的な考え方です。 もう立ち上がって歩いているお子さんでも たとえば、以下のようなことは ・床との付き合い方 もう歩けてるからといって 横になった状態からはじめると そのときの「新しい情報」は、 あお向けで寝ている状態の赤ちゃんを先生にして
このレッスンでは、 細かな動き、小さな動きを「意識する」ことで 大ざっぱな地図をもとに子どもを見ていると 詳しい地図を手に入れることで |
【Zoom】赤ちゃんの動きから学ぶ体と発達 楽しい「あぐら」 ~骨盤と背中の動き~
※このイベントは終了いたしました